【特集】シャープ×VTuber「さくらみこ」コラボ家電の“愛が凄すぎる”舞台裏――担当者に聞くこだわりと“喋る家電”の未来
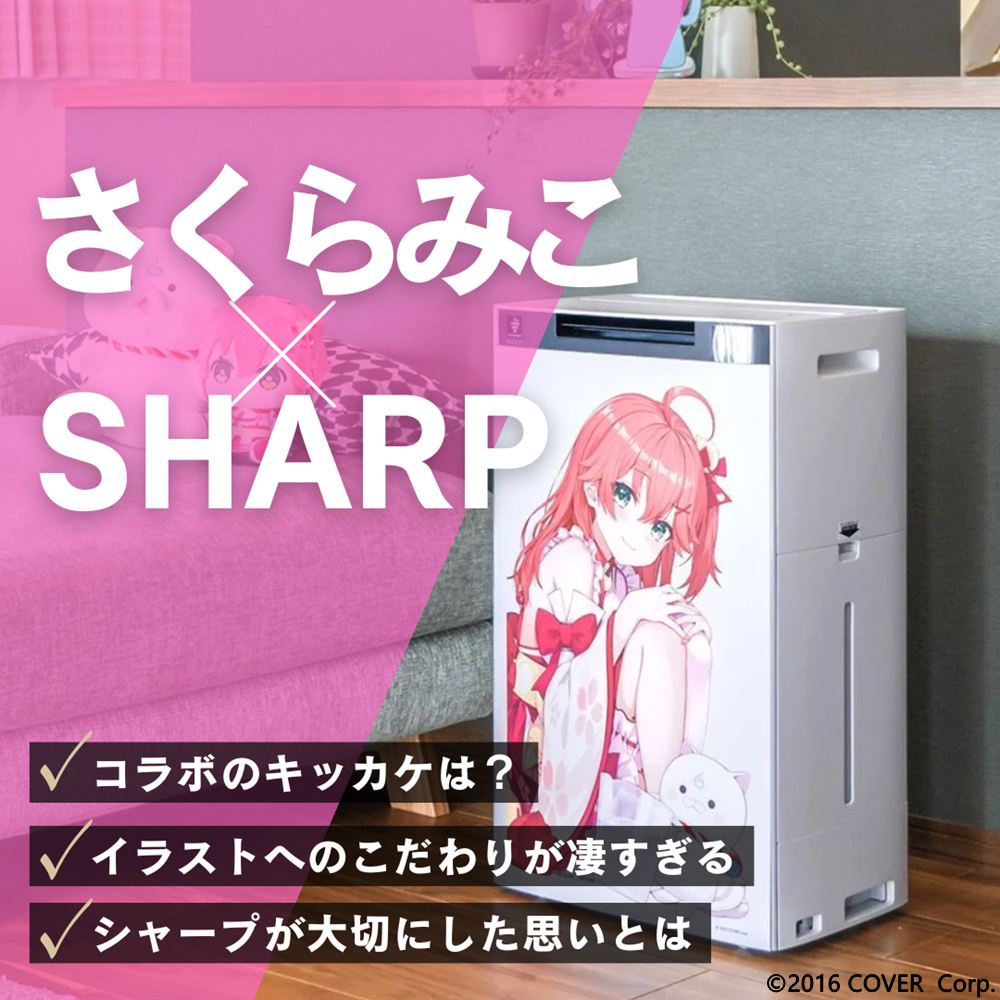
「やはり、お堅く歴史のある会社というイメージがあります。なので、じっとしていかなければいけないのかなと思っていたので、案外エンタメができる会社で驚きました。それはこの部署が特殊というのもあるかもしれません。ちゃんと話を聞いていただいて、実現に向けてお力もいただいたので感謝しています」(児玉氏)
「児玉が持つ熱量に、再発見することが多かったです。規格外のアイデアがバンバン出てきて。『どうしてもこれを表現したいんだ』という気持ちが、何かを話すたびに伝わってくる。この取り組みは熱量が第一ですので、すごくいいなと感じていました」(徳永氏)
そんなシャープにおける喋る家電の取り組みは、10年以上前から始まっている。当時発売していたロボット家電「COCOROBO」に、音声認識のボイスコミュニケーション機能による対話操作などを搭載したモデルを発売していた。
徳永氏によれば、家電における性能勝負や価格競争のみならず、人間は無生物に対して親しみを込めて大切に扱うようなことがあっても、その対象に家電が入っていないと感じていたことに危機感があったと振り返る。
「例えば車が好きであれば愛車、本が好きであれば愛読書と呼ばれていますけど、家電に対して“愛家電”とは言わないと思います。どのように愛される家電の製品作りをしたらいいのかを考えたときに、魅力的な音声で喋る家電があれば、そのように思ってくれるのでは、と思ったことが始まりだったと記憶しています」(徳永氏)
そして喋る家電の取り組みで大きな転機となったのは、2014年に試作した「プレミアムなCOCOROBO<妹Ver.>」。これはツンデレの妹系オリジナルキャラクター「ココロボちゃん」を制作し、漫画家によるかわいいイラストと女性声優によるボイスを搭載したもの。あくまでモニター利用者の反応を伺う研究開発が目的で市販の予定はなかったが、ニュースとして報じられると反響が大きく、モニター募集10人に対して100倍以上の応募があるなど話題にもなり、受注生産による販売を決定。さらにアニメやゲームとのコラボモデルも発売した。後にCOCOROBOは生産終了となるが、この流れを受け継いだのが「COCORO VOICE」や、カスタマイズサービスとなっている。
「私や安田が取り組み始めたときは初めてのことだらけ。役職が上の方や先輩の方々に、なかなか理解者がいなかったので、ひとつひとつ説得していかなければいけない状況でした」(徳永氏)
徳永氏によれば、10年前はまだ喋る家電というのは物珍しく見られていたところがあったとしているが、今はシャープとしても音声を発する家電そのものを数多く発売していることや、COCORO VOICEについても対応しているのが4機種(ヘルシオ、ホットクック、空気清浄機、洗濯機)あることなどを理由に、だいぶ浸透してきていると感じているという。
「実際にユーザーアンケートをとると、非常に高い評価をいただいていますし、魅力ある音声が搭載されている家電製品は、長い間ユーザーが活発に利用してくださっているということが、データとしてもわかっております。アクティブ利用率が高く、大切に扱っていただいているものと認識しています。そして、今の時代にとってはとても価値のあることだと感じていますし、ボイスサービスをやってきてよかったと感じています」(徳永氏)
そんな喋る家電を長年展開していくなかでの知見や大切なことについて聞いたところ「制作にあたって、台本(セリフ)のクオリティに徹底的にこだわること」を挙げる。
「まずはその作品の勉強をします。原作を読んだりアニメを見たり、購入できるのであれば台本を取り寄せてみたり、その後台本制作に入ります。そこまでやらなくても良いという意見もあるのですが、僕はお客様に顔を向けた開発を意識していて、この気持ちが無いとうわべだけの取り組みに気づかれて「浅い」とがっかりされてしまう。それはビジネスという面からも長く続かないだろうと思います。人に寄り添う家電を本気で考えているのはシャープだ、とお客様に言っていただけるように取り組んでいます」(児玉氏)
技術の進化によって、家電そのものも喋る家電についてもできることの可能性は広がっている。徳永氏は10年前に元シャープの方が書いた書籍において、将来の家電について「喋ること」、「ネットワークにつながること」、「人格を表現できるAIを持つこと」の3つが大切になると記載していたことに触れつつ、今はさらなる先端技術の登場によって、この3つにとどまらないことができる時代になっているという。これを踏まえつつ、児玉氏、安田氏、徳永氏が喋る家電の未来像について語る。
「僕はずっと“エンタメ家電”と呼んでいるのですけど、エンタメは生きていく上で絶対に必要なものではなく、ある意味“余計なもの”なのですが、人間はそういうものが好きだと信じています。そもそも家電にボイスというのは、機能として絶対的に必要かと言われるとそうではありません。でも余計な一言があるから楽しかったり、嬉しい気持ちになったりします。僕は、その余計なことや、やらなくていいことができるということに家電の未来があると思っていますし、我々がやっていることの価値はそこにあると考えています」(児玉氏)
「シャープにおける喋る家電の取り組みの今後については、どのような発話が喜ばれるのか、そして長く愛されるものにしていくか、その探求は続けていきますし、COCORO VOICEを含めたサービス品質の向上に取り組んでいきます。コラボレーションについては、日本国内だけでもものすごい数の人気作品、そしてキャラクターが存在していますし、新しいコンテンツもどんどん生み出されていっている状態でもありますので、それを踏まえていろいろな組み合わせを考えた商品を提供していきます。そもそも音声というのは、人類が文字を発明する前からある根源的なもので、単なる情報伝達だけではなく、喜びや悲しみの度合いも豊かに伝達ができる素晴らしいもの。先端技術があふれる時代になったからこそ、音声の力の価値が見直され高まっていると感じていますし、少なくともシャープはその力をよく知っている会社ですので、時代にあわせて、喋る家電、そして喋るサービスというところも含めて、広げていけるだろうと思っています。さらに家電の枠を超える、とどまらないチャレンジもしていきますので、引き続き注目していただきたいとみなさまにお伝えしたいです」(徳永氏)
「技術進化やAI周りの進化によって、家電そのものの機能のみならず、この先いろいろなことをわかって先回りして賢く発言ができる、気づきを与えられるような、機能的な価値を持つ喋る家電というのも出てくるでしょう。それが人に寄り添う家電のあり方かもしれませんが、求められているのはそれだけではなく、『人“が”寄り添いたくなる家電』。言葉を変えると愛着を持つことであって、その方法論のひとつに、今取り組んでいるCOCORO VOICEなどのサービスのように、好きな声で喋るということがあります。そして寄り添いたくなるものには、かわいいであったり、余裕や隙があったりというような、本来であれば必要のない味付けの部分もあったほうがいいのではと。業界的には“より賢く”という流れになっていくと思いますけど、人が寄り添う家電を受け入れられるような形を作っていくことも大事だと考えます」(安田氏)



 購読
購読 配信
配信 RSS
RSS